私たちが当たり前に使っている言葉でも一般の人が聞くとなにそれ?という言葉が数多くあります。
今回の「ヒネモノ」も魚の市場でよく使われる言葉です。
塩鮭を買うときとかいくらの醤油漬けを買うときとかに出てきます。
別に隠語というわけではないのでしょうが一般の人にはわかりにくい言葉ですね。
漢字にすると陳物(ヒネモノ)と書くようです。
この言葉知っておくとなにかと便利なこともあると思うので今回はこの言葉の実例を紹介しながらの説明してみたいと思います。
ヒネモノとは?

ヒネモノとはデジタル大辞泉によると、
ひね~もの【陳物】
古くなった物。また、売れ残った物。
デジタル大辞泉より
というようです。
weblio辞書では
【陳者】ヒネモノ
経験を積んで老獪になった者
weblio辞書
これだとなんかひねくれた人みたいですね。
水産業界で使うヒネモノは前者に近いです。
ただ、少し実務上はニュアンスが違うようです。
水産業界ではよく使う言葉
水産業界特に市場ではこの「ヒネモノ」という言葉を実によく使います。
簡単に言えば前の年に作った水産品のことです。
それも冷凍物か乾物の場合に使うことが多いです。
たまに塩数の子などのことにも使うこともあるので必ずしも冷凍物に限定というわけではありません。
水産品は季節性の強いものが多く獲れる時期が限られているものが結構あります。
そしてその水産加工品をその魚が獲れる時期に一気に一年分作ることもよくあります。
例えば、いくら醤油漬けや身欠きニシンなど。
それが一年のうちにすべて完売するとは限りません。
そうすると作る時期には前年の残りというものが発生することになります。
これが前年の在庫品すなわりヒネモノということになります。
なので常時継続して作り続ける加工品は前年の在庫があるという状態も少なくいつも商品が回転している状態にあるのでヒネモノという言葉を使うことは少ないようです。
ヒネモノは必ずしも安くなるとは限りません。
前年の在庫であるならヒネモノは当然値段が安くなるというわけではありません。
ヒネ=叩き売られる というものではありません。
結局次の年に極端に漁獲量が減ってしまうようなことがあるからです。
そうすると前年のものでもいいから欲しいという人が出てきます。
※ちなみに塩干冷凍品の冷凍賞味期限は大体2年です。
結果的に価値が上がり相場値段も上がることもよくあります。
その逆に大量に獲れたりしてもメーカーかおろしが前年の在庫を持っていると生産量を調整したりします。
結局最初のうちは値段も下がらず高いままでしばらくいく時もあります。
流石に後半は下げてくるでしょうが思ったより安くない時などよくあります。
結局大きなメーカーやパッカーがイニシアチブを持って価格調整している訳です。
そのメーカーやパッカーもいつも儲かるわけではなく損することもよくあるようですがまあ大きな損はしないようになっているのかもしれませんね。
ヒネモノにはどんなモノがあるか見てみましょう!
実際にどんな水産加工品にヒネモノがあるのでしょう。
写真付きで見ていきましょう。

新巻鮭
塩干加工品
秋鮭が秋にしか獲れないのでその時期に一気に作ります。
それ以降はヒネモノを使っていくという感じになります。

いくら醤油漬け
冷凍加工品
これも鮭が秋にしか取れないのでその時期にしか作れません。
ヒネモノの代表選手といえます。そしてヒネモノの方が高いということもよくあります。


有頭エビ
水産冷凍品
年末に使う煮えびに使いますが残ったらヒネモノになりこれもたたき売られる存在になります。

子持ち干しガレイ
塩干加工品
一般的なカレイは常時作り続けるのでヒネモノは発生しにくいです
しかしながら、このような卵を持ったカレイの場合は春先にしか作れないのでヒネモノが発生する可能性があります。

塩蔵わかめ
塩干加工品
海藻類も採れる時期が限られているためヒネモノが発生します。
こうやってみるといろいろありますね。
ちなみに米や農産物もヒネモノが発生する場合があり得ますがあまりヒネモノとは言わないようです。
コメに関していえば古米という言い方になるのでしょう。
農産乾物はヒネモノというのでしょうか?正直よくわかりません。
最後に
一年通して安定供給するのはとても難しいモノです。
冷凍や塩蔵して保存しようとした昔の人たちの努力知恵は尊敬に値します。
仕入れを担当する者としてはこのヒネモノについての扱いは非常に敏感になります。
価格、品質、数量など総合的に判断しなければいけない意味でヒネモノは非常に扱いが難しいです。
最近は賞味期限が入っているのでその点はわかりやすいですが、現物を見ずに商談することもあります。
その時はいろんな情報を聴きながらそれに見合った価格を設定しなければなりません。
ヒネモノを扱うには相当な経験と判断力が必要なのです。
いわゆる概して塩干商品になりますがこれが故に塩干の買付が難しいと言われる所以ですね。
鮮魚を扱う方がどれだけ楽かわかりません。
これを機に塩干冷凍品の仕入れの難しさがわかっていただけるとありがたいです。
みなさんにはまず、このヒネモノという言葉の存在を知っていただくことが先ですね。
<終わり>

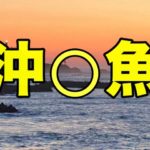







コメントを残す