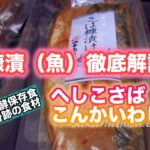みなさん、納得の刺身盛合せを作れてますか?
刺身盛合せはその店の技術レベルが結集されているところでもあり、みなさん日々鍛錬されてきたところだと思います。
特にお盆や年末はスーパーにおいても刺身盛合せの最重要需要期です。
この刺身盛合せをいかに売るかによってお盆期間、年末期間の鮮魚の売上が左右されます。
その意味で刺身盛合せ作りということが重要になってきます。
そこで今回刺身盛合せを作る上で重要なポイントを3つ紹介します。
目次
刺身盛合せの売上を上げるのはチラシでも値引きでもない
まず前提の確認です。
刺身盛合せの売上を上げるのはチラシでも値引きでもないということです。
刺身盛合せを売るために大事なことはお客さんの信頼を得ることです。
これは絶対的です。
お客さんの信頼を得られている状態を「ストアローヤリティ(信頼)」が高いといいます。
これが低い店は刺身盛合せの予約も少ないのです。
もし刺身盛合せで評判得たいなら、『刺身盛合せを頼むならこの店』にならなければいけません。
そのためにも今回紹介する5項目をしっかり意識しなければなりません。
これを押さえるだけで刺身盛合せのイメージがガラリと変わります。
ぜひ今から説明する内容を覚えてください。
刺身盛合せ造りの重要ポイント5選

刺身盛合せ造りのポイントはいくつかありますが重要なのはこの5項目です。
- 大根のケン(敷きツマ)の使い方
- 山のバランス〜点と線
- 色のバランス
- 刺身の切り方
- 解凍のタイミング
重要な順に並んでいます。
それぞれ解説します。
大根のケン(敷きツマ)の使い方 〜ポイント1

刺身盛合せで一番需要というか見栄えに差が出るのが大根のケンの使い方です。
その意味でここが一番重要と言えます。
刺身の切り方も重要ですが結局のところのこの大根のケンの使い方、盛り方で決まります。
逆にいうとケン使い方が上手ければ刺身が上手に見えるのです。
その上で大事なことは、立体陳列という手法です。
手前を低くく奥を高く立体的に盛り付ける
こうすることとで刺身が凛と品格が上がっていきます。
逆にダラッ〜と刺身が寝ていてはいい刺身に見えません。
立体感を意識しましょう。
まずこの大根のケンの盛り付け方をしっかりマスターしてください。
具体的には、次の4つです。
- 大根のケンは個別の山にする
- 大根のケンは一握りで楕円にする
- 奥を高く、手前を低く
- 大根のケンは見せてはいけない
これだけだとわからないと思うので少し解説します。
大根のケンは個別の山にする
山は個別に盛り付けるものです。
この点関西などでは平に敷いたケン(ツマ)に盛り付けたりするところもあります。
効率を重視するやり方です。
しかし見栄えを良くしたいときは平に敷くのではなく、1個づつ山を作るべきです。
個別の山に盛り付けるというのが刺身盛合せの基本と考えてください。
大根のケンは一握りで楕円にする
そして大根のケンは一握りで楕円にするのがコツです。
ケンの量は片手で握って手の中に収まる程度です。
大根のケンを置いてあるボールから片手で持って包丁で切り落とす感じです。
リズムよく一回で形が決まるのが理想です。
手前を低く奥を高くする

刺身の盛合せは奥を高く手前を低くして立体的に見せるのが基本です。
他のスーパーの刺身盛合せを見ると奥の方にだらしなく下がっているのをよくみます。
刺身のそれぞれが後ろにお辞儀していたりするのです。
これでは緊張感ない盛合せになってしまい台無しです。
キリッとした刺身にするためにも立体感を意識しましょう。
ここは先ほど説明した大根のケンの盛り方が影響しています。
大根のケン自体、手前を低く奥を高くして置くように意識しましょう。
その前提として奥から刺身を盛り付けるようにしましょう。
上の写真はスーパーの刺身ではありませんがイメージとしてはこんな感じです。
高さがあってもフタは閉まらないことはないので心配ありません。
大根のケン、敷きツマは見せてはいけない

最終的に大根のケン、敷きツマを見せてはいけません。
大根のケンはパンツのようなものと言われることがあります。
白いケンが見えてしまっては非常に恥ずかしいものです。
一般の人も気づかないかもしれませんが上級レベルになるとここもしっかり意識しなければいけません。
どうしても見える部分は後でパセリや海藻で隠しましょう。
ただこれは最初に作る大根のケンの山の大きさにも関係します。
出来るだけ小さく作るように心がけましょう。
山のバランス 〜ポイント2

刺身を盛り付ける山は個別に作りましょうとご案内しました。
その場合、その山が整然と規則正しくと並べられているのが理想です。
ところが現実は山のバランスが悪くなっていることがあります。
自分で上手に作れたと思っても周りの人に評価されないのはこのバランスが悪いからです。
これは点と線を規則正しく並べると意識するとキレイになります。
詳しくは過去に記事を書いているのでそちらでご確認ください。
刺身の切り方 〜ポイント3

刺身の切り方ももちろん重要です。
ポイントは次のとおりです。
- 刺身盛合せは基本平作り
- 幅、厚さは等間隔に
- 刺身の長さを同じにする
- 刺身一切れのグラム数
- 切り数は奇数
- 角が立った刺身
刺身盛合せは平作り

刺身盛合せは平作りが基本です。
最近のスーパーでは比較的技術のいらない削ぎ切りが流行っていますが削ぎ切りはだらしなく見えるので盛合せには本来向きません。
若い層が多いスーパーならそれでもいいでしょうが本格的な刺身盛合せとして評判になるようにするならキリッと角のたった平作りの刺身盛合せにするべきです。
もちろんネタや状況によってソギ切りする場合もありますが可能な限りヒラ作りでするようにしてください。
幅、厚さを等間隔に

平作りで作った場合、刺身の幅、厚さが均等になっていないといけません、
厚かったり薄かったりするのは技術がないからです。
リズミカルに切れるようになれば自然と厚さは均一になっていきます。
リズムよくを意識しましょう。
刺身の長さを同じにする

魚は尾の方に行くに従って幅が短くなります。
包丁を真っ直ぐに切っていくと必ず尾の方の刺身の長さが短くなります。
特に初心者の場合は顕著です。
上の写真のように長さが不揃いはダメです。
包丁の角度を斜めにしたりしてして調整しましょう。
ただこの技術レベルは非常に高いので意識して繰り返し練習しましょう。
刺身一切れのグラム数

一つあたりの刺身一切れのグラム数は各店で決まっていると思います。
通常は10〜12gです。
切り方によってはしょぼくもなるし立派にも見えます。
大きめにするときは15gまででしょう。
一切ずつ量れればいいですが時間がないときは山単位で確認すればいいです。
慣れれば大体の重量わかるようになります。
いわゆるここがしっかり管理できてないと利益も垂れ流しになるので普段から神経使いましょう。
検定があるところもありますが、意識しすぎて時間が遅れ遅れになるならスピードを優先したほうがいいようにも思います。
ここは企業で考え方が違うのでなんとも言えないところです。
切り数は奇数

縁起を担ぐ場面で食べる刺身盛合せの切り数は奇数であるべきです。
知らない人も多いと思いますが昔からそういう言い方をされています。
ここは刺身の流派などに関わりますが深く考えずに奇数が基本という知識だけでも持っておけば十分です。
しかし最近はそんな縁起は気にせず値段を優先して偶数にする場合もありますのでその時はお店の指示に従ってください。
角が立った刺身

信頼される刺身盛合せの刺身は角が立っています。
もちろんヒラ作りで切る場合です。
削ぎ切りにして角が立つという言い方はしません。
これは素材の鮮度もありますがテクニックでもあります。
ヒントは包丁を背を少しだけ左に向けて切ると角が立ちやすいです。
①包丁の背を少し左に向けて、②包丁の刃元から入れ、③滑らすように全体を使って、④包丁のおもみで切って、⑤かえすと切り口もキレイになり角がたちます。
この技は結構使えますよ。
規則正しく並べる

刺身を切ったらそれら規則正しく並べるとキレイに見えます。
刺身の端を点とみてそれを繋げてみると規則正しく並んでいるかどうかがわかります。
下の記事に詳しく書いてありますのでさらに深く知りたい方はこちらの記事をどうぞ。
色の配置 〜ポイント4
目立つ色を左に配置

目立つ色を左に配置するのが基本です。
人の視線の動きというものは左から右に移動するものだからです。
目立つ色は赤色です。
赤色の刺身といえばマグロですね。
すなわちマグロの刺身を左に配置するのが映える刺身になります。
しかも奥の方から視線が斜め下に移動します。
なので二列三列にする場合は左の奥に置くのが正解です。
解凍のタイミング 〜ポイント5
刺身盛合せづくりではこの解凍のタイミングが一番重要かもしれません。
刺身盛合せはお盆や年末に集中します。
材料もそこそこの量になります。
なので事前の準備が非常に大事になります。
特に解凍が必要なマグロやサーモンは切る時にベストな状態にしておく必要があります。
初心者が失敗するとしたらココです。
この解凍品はとかしすぎてもダメだし硬すぎてもダメなのです。
適度な硬さにするタイミングが難しいのです。
解凍タイミングが悪いとどうなるか
計画的にしない解凍しないと固く凍ったサクを使わないといけなくなります。
特に冬場はなかなかとけてくれなくて四苦八苦します。
そうなると硬いし、大変だし、時間も遅れ遅れになります
また、慌てて解凍してもいざ切ろうとする時に芯が固かったりスライスしたものが並べにくかったりします。
しまいにはバラバラにまとまりなくなったりします。
しかも刺身自体も水っぱいものになってしまいます。
とりあえず切れたとしてもトレーの中がドリップだらけになってしまいます。
家に持って変えるとドリップが刺身トレーの底に溜まっていたりして買った人は残念な思いをします。
クレームになることもあります。
最悪次の注文がなくなる憂き目にあったりするのです。
溶けすぎても切りにくい
また、逆に溶けすぎても切りにくいものです。
溶けすぎたものはリズム良くきれずに結局製造スピードが遅くなってしまいます。
適度な解凍状態というものがあるわけです。
その意味で刺身盛合せは解凍の段取りが非常に重要なのです。
付け加えると、養殖物も一緒です。
必要な分を計算しておかないと後一山、一切れ足らないために、急いでブリをおろさないといけないという羽目になってしまいます。
その他チェック項目

刺身盛合せは他にもテクニックがあります。
そのほかのポイントもチェックしておきましょう。
刺身盛合せはスピードが命

とにかく最需要期の刺身盛合せはスピードが命です。
段取りよくしなければ時間までに間に合わずお客さんに迷惑をかけるということもあるのです。
一つの失敗が全体に響いていくものです。
自分たちもオロオロになってしまわないように解凍タイミングだけでなくおろしものなどの刺身材料の準備はしっかり計画しておきましょう。
そのためにも当日使う分はスタートの時点で9割がた用意しておくこと。
具体的にいうと必要なものを解凍し、おろしものをおろして皮を引いておくということです。
残りの1割で微調整するようにしましょう。
例えば冷凍物であれば完全に溶かさず冷蔵庫に移しておいたりということです。
もし使わなくても少ししか解凍してなければまた冷凍庫に戻せます。
ただしマグロは少しでも解凍したら使ってしまわないといけないなので最後に判断します。
盛合せに使うサク選び

特に盛合せには形のいいサクを使いましょう。
出来るだけ長方形の幅調整をしなくてもいいサクを使いたいです。
三角形や台形のサクはできるだけ店売りに回しましょう。
刺身盛合せに入れてはいけない刺身

刺身盛合せはハレの日に食べるものです。
家族で集まったり、大切な人をおもてなしたりする時に使われることが多いものです。
おかしな刺身盛合せだったら買った人のメンツも丸潰れになります。
なので次の刺身は入れないようにしましょう。
- スジや打身の跡がある刺身
- スルメイカ、カツオたたきなどの安いネタ
- 鮮度のおちた刺身
特にバチマグロのスジや血栓には注意したいところです。
こういうお刺身本当に使うことあるのかと思うかもしれませんが結構使っているところがあります。
まさにしっかりとした指導がないスーパーなどです。
刺身担当者に任せっきりだったりします。
本人が悪いというよりそこまで目が届かない体制が問題なんだと思います。
次から買わなければいいだけなのですが同業として残念な思いになります。
私の先輩で盛合せが売れず5点盛りを6点盛りで同じ値段にしたら売れるだろうと言ってサービス盛合せ作っていた人がいました。
その盛合せをみたら上の3点が入っていました。
売れるわけないですね。
そもそもの考え方が違うと思いました。
まとめ
スーパーでもちゃんとした教育体系があるところばかりでありません。
ちゃんとした教育体系があるところでも集団講義で一回説明して終わりといった感じです。
実際にやる時にわからないということが往々にしてあると思います。
刺身を教えてくれるコンサルに依頼するとなかなかな料金もかかります。
じゃ先輩に聞いたらどうかというと、魚屋特有の細かい技術は他の人には教えてくれないという悪しき慣習があります。
でも刺身を作る人たちはもっと色々知りたいわけです。
「さかなのさ」はそんなやる気のある人たちを応援したいわけです。
なのでこういった感じで無料で有益な情報を提供しているのです。
この書かれている内容を見て勉強してぜひ自分達の手柄にしてほしいのです。
また企業に対しても応援したいと思っています。
しっかりと刺身を強化したいという強い想いがある企業様でしたらご相談の上協力させていただきます。
鮮魚の運営に関してはまだまだ経験に裏付けされたノウハウたくさんあります。
どうぞお気軽にお声をおかけください。
<終わり>