超わかりやすい鮮魚の計数管理シリーズ第2回目です。
数字の話はある程度会社なりお店なりで教えてもらう機会はあると思いますが、その場だけではよく理解できないという人たちのためにここでポイントを押さえて解説しています。
もともと魚屋さんは昔から机の上でする数字の勉強が苦手という人が多いです。
なので出来るだけ噛み砕いてわかりやすく解説しようと思います。
今回は構成比という言葉を説明します。
正確にいうと部門売上高構成比です。
ポイントはこの部門構成比を理解することで売上アップにつなげられるということです。
何を意味する数字でしょうか。
この意味がわかると現場での数字も使いやすくなると思います。
鮮魚の構成比とは
構成比というのは読んで字のごとく全体に占める割合を%で表したものです。
いろんな場面で使われます。
部門の売上高を基準にする場合や部門の中のカテゴリの売上高を基準にするものなどあります。
具体的に見てみましょう。
パターン1 対部門構成比
例えば、鮮魚部門、精肉部門、青果部門、その他の売上の割合を見るときは店全体からその割合を出します。
店全体売上高 300万円
鮮魚売上高 30万円
精肉売上高 42万円
青果売上高 36万円
その他売上高 192万円
※リアルではなく仮の数字です
1日の売上高が上記のような場合に
鮮魚 10.0%
精肉 14.0%
青果 12.0%
他省略
※リアルではなく仮の数字です
という構成比になります。
これを部門売上構成比と言います。
※リアルではなく大体の数字です
パターン2 対カテゴリ構成比
同じように鮮魚部門での構成比を見ます。
鮮魚売上高 30万円
刺身売上高 7.5万円
切身売上高 4.2万円
生魚売上高 9万円
その他売上高 9.3万円
※リアルではなく仮の数字です
1日の売上高が上記のような場合、
刺身 25.0%
切身 14.0%
生魚 30.0%
他省略
※リアルではなく仮の数字です
という構成比になります。
これを分類別売上構成比ないしはカテゴリ別売上構成比と言います。
会社によって名称は変わると思いますが部門の中の構成比です。
いずれも売上高を見れば売った金額が多いか少ないかわかりますよね。
ではなぜ構成比を見るのでしょう?
なぜ構成比を見るのでしょうか?
なぜ構成比を見るのかというと、
日によって売上高変わっても同じ基準で見たいからです。
例えば、パターン1であげた店全体の売上高は300万円としましたが、次の日は320万円になるかもしれません。その次の日は280万円かもしれません。
当然部門の売上高も日によって変わります。
そうすると部門の売上高や分類の売上高でみても毎日違っていてわけわからなります。
実際の金額だけ見ても比較できませんね。
それでは困るのでそれを同じ基準にするために構成比という割合を使うのです。
構成比は朝の数分で把握するもの
みなさんは毎日売上日報を見ると思います。
名前はいろいろあるかもしれませんが毎日の売り上げをつけた帳票のことです。
一般的なスーパーマーケットだったりするとこの構成比が出ていると思います。
そこで構成比を確認できるのです。
それは売上高が毎日違うとしても一定の割合として部門の売上(業績)がでているわけです。
毎朝、売上日報を見るときに構成比を見て昨日の業績が他よりもよかったのか悪かったのか見て反省分析してその当日の作戦に生かすのです。PDCAサイクル
朝のちょっとした時間で判断します。これが大事なのです。
正しい構成比はどのくらい?
毎日見ていると自分の部門の構成比がわかるようになってきます。
水産部門だとどのくらいの構成比が必要なのでしょうか?
鮮魚のあるべき部門構成比はどのくらいの割合でしょう?
ほとんどの店が
大体9.0〜10.0%といったところでしょうか。
立地場所や得意の部門の違いなどで数値は変わりますが一般的にはこのくらいの構成比になると思います。
ただ正直リッキーの提唱する「攻める鮮魚理論」ではこの数値では物足りないです。
これについては以前に記事を書いていますのでこちらも参考にしてください。
また、構成比は曜日別での把握も必要です。
曜日によって指数が変わって当然ですから。
例えば週末は鮮魚の部門構成比は下がるものです。
魚の入荷がないですし、グロッサリーが大きな売り込みかけるから平日より下がるという傾向があります。
またカテゴリで見ても週末は生魚の売上が減り、刺身が増えるというのもわかりますね。
逆に平日は鮮魚の部門構成比は上がりやすいですし、生鮮魚カテゴリの構成比も上がります。
曜日別での特性を把握するということも売上アップには大事なところと言えます。
部門構成比の本当の意味
で、数字の把握としては以上ですが、私はこの構成比の意味を次のように考えます。
鮮魚部門が頑張ったかどうか
を見る基準と考えます。
よくあるのが昨日は雨が降ったので魚が売れなかったとか競合店が大きなチラシを入れてあったのでダメだったとかいういって言い訳する場合があります。
しかし構成比を見ればその部門が頑張ったかどうかわかるわけです。
つまり部門構成比の基準があるとして、それより高ければ頑張ったといえるし低ければ頑張っていなかったという評価ができるのです。
それにもかかわらず、さも売れなかったのが他に原因があったようなことを言い訳していてもこの基準を持ってこられると反論の余地がないわけです。
いやいやあなたが頑張ってないだけですよ!ということです。
実際に構成比を見ればしっかり頑張っていたかわかるということです。
本当に店全体で他の影響を受けたなら構成比は変わらないはずですから。
そのようにしてこの構成比を見るのです。
例えば日曜日の平均構成比が9.0%だとして、実際部門の構成比がそれ以上なら頑張っていたと言えますし、それ以下なら何やっていたのということになります。
構成比11.0%もあったらよく頑張ったな!と褒めてあげられるわけです。
逆に売上高がよさそうに見えて昨対を超えていたとしても構成比が低ければ何をしてたのということです。
このようにして構成比を使うのです。
売上高の増減に惑わされない客観的指標なのです。
鮮魚構成比のベースを上げるには?
ではこの鮮魚の部門構成比を上げるにはどうしたらいいでしょうか?
これは店全体の生鮮強化対策につながるという意味で非常に戦略的に重要なところです。
しかも利益率の高い鮮魚部門の構成比を上げるということは店全体の利益の底上げにもつながります。
その中で鮮魚の構成比を上げる手法はもう既に確立しています。
ただ項目が多すぎてここでは書き切れません。
このブログでこの点について既に記事にたくさん書いてきています。
ぜひこちらを参考にしていただけると幸いです。
手短に聞きたい方はLINE無料相談またはメールでの直接相談の方でお声かけください。
ヒントをあげるとしたら「鮮度の信頼をあげる」ということに尽きるのではないでしょうか。
\ 本質がわかれば確実に売上アップします! /
\ なぜ30万円なのか? /
まとめ
この構成比は簡単にいうと客観的な事情に左右されない部門の頑張り具合を見る指標の一つです。
例え夕方激しく雨が降っきて来店が減ったとしてもこの構成比が上がっていればその部門は他の部門より頑張ったと言うことです。
単純で簡単に見れる割に結構日々使える指標の一つです。
でも意外とないがしろにされているようにも思えます。
意味や使い方がわからないからでしょうか?
この記事をご覧になられた方はここでその意義や使い方をマスターしていただけるとありがたいです。
これはどんな商売にも使える指標ですのでいろいろ使ってみてください。
難しい言葉を使って知ったようなことを言うくらいならこのような基礎的な言葉の意味をしっかり理解して使っていったほうが何倍も役に立つと思います。
わかりにくい点、不明な点ありましたらメールまたはSNS に連絡ください。
また現在有料のコンサルはしておりませんがアドバイス程度の相談は受け付けておりますので石川県外で店舗運営や水産経営でお悩みの方はお気軽にご一報ください。
次の記事はコレ>>第3回「鮮魚のロスの意味」
前の記事はコレ>>第1回「売上高の構造」
<終わり>
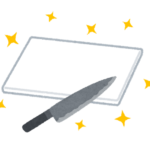








コメントを残す