水産業界で使われる基礎的な用語を集めました。
今魚屋で知っておいてほしい言葉です
ぜひ使ってみてください。
クリックで見出しに移動します。
アニサキスフリー あやかり鯛 SKU 沖のついた魚 魚貝類と魚介類 K値 消費期限と賞味期限 鮮度と鮮度感 縮み(ちぢみ) 調理と料理 二杯酢・三杯酢・土佐酢 煮干しと田作り NET ばけ ヒネモノ 身焼け・ノリ・白太 ユニットプライス
※気になるものあれば順次追加していきます。
目次
言葉の統一を意識しよう!
前提として考えて欲しいのは言語統一の重要性です。
言葉の意味をみんなで共有しないとその組織のレベルが上がらないものです。
ただ魚屋では言葉が曖昧です。
個人の我が優先されたりもします
それを防止するためにも強い意志を持って言語を統一化を図っていきましょう。
では、はじめましょう!
アニサキスフリー
アニサキスフリーはアニサキスの心配がないという意味です。
魚についていうとアニサキスの被害を受けにくい魚ということです
比較的新しいキーワード。
刺身とアニサキスの問題がクローズアップされてから使われるようになりました。
アニサキスについての関心が大きいことを象徴するような言葉ともいえるでしょう。
詳しくは下の記事をご覧ください
あやかり鯛
鯛とついているのにタイ科の魚でないものを「あやかり鯛」といいます。
車鯛、金目鯛、石鯛、甘鯛など。
私も最初はこういう言葉があることを知りませんでした。
まあ、だからどうだってことなのですが、魚屋さんとしては押さえて置きたいところです。
下記の記事で詳しく書きましたのでこちらをご覧ください。
SKU
SKU(エスケーユー)という言葉をご存知ですか?
Stock Keeping Unit の略です。
受発注や在庫管理の最小単位のことです。
スーパーでいうとパックの種類のことです。
鮭の切身があるとして、2切パック、3切パックをそれぞれ1と数えてその数の多い方がいいとされる売場の在庫管理基準です。
なぜこの「SKU」使われるかというと、お客さんが選びやすくなり、結果的に売上が良くなるからです。
SKUが多ければ多いほど売上が上げられるという理論です。
少ないアイテムで多く品揃えがあるように見せる技術ともいえます。
なのでSKUを増やしなさいと言われるのです。
似たような言葉に「アイテム」という言葉があります。
「鮭の切身」がアイテムです。
商品名と思ってもらって差し支えありません。
これも多い方がお客さん選べていいということになります。
具体的にいうと「鮭切身」のことです。これだけだと1アイテムになります。
鮭の切身が2切、3切、4切のパックがあるとすると1アイテム3SKUあるということになります。
同じ売場にブリの切身があると2アイテムになり、
これも2切、3切、4切のパックがあるとすると全部で2アイテム6SKUあるということになります。
お客さんは6つの選択肢があることになりより買いやすくなります。
SKUの意味わかりましたか?
ちなみにSKUの究極がユニットプライス(後述)です。
グラム売りのことでそろぞれ量目違うのでパック数だけSKUがあることになります。
沖のついた魚
「沖ブリ」とか「沖あんこう」と名前の先頭に「沖」のついた魚ご存知ないですか?
これ偽物の魚です。
ブリでないしあんこうでもない魚のことです。
昔よく使われてきました名称です。
まれに沖甘鯛のような正式名称もあるのですが、それ以外は今はこういう表記ダメなのです。
意外と魚屋さんでも知らない人多いです。
知らなかった人は注意してくださいね。
詳しくは下記の記事でご覧ください。
魚貝類と魚介類
魚屋さんでは魚貝類と魚介類どちらを使うのが正しいのでしょうか?
ベテランだからわかっているというようなものではなさそうです。
ヒントは魚介類の方が広い概念だということです。
魚屋で使うとしたら、
魚介類
が正しいです。
【理由】
魚貝類といった場合は魚と貝のみの狭い意味になります。
しかしながら魚屋でエビ、いか、たこ、カニ抜いて話をするわけにはいきませんね!
海藻も含める必要があります。
魚介類は魚貝類より広い概念になります。
したがって、魚屋では甲殻類や海藻類も含む「魚介類」を通常使います。
ちなみに介は「助ける」の意味があり、甲羅や貝殻などの硬いもので身を助けるものという意味で甲殻類、貝類を指すといわれています。
K値
「K値(ケイチ)」といういう言葉ご存知でしょうか?
魚屋らしくない言葉で知らない人も多いかもしれません。
しかし、このK値は魚の鮮度を話すときに必要な言葉です。
鮮度を科学的客観的に把握できる数値です。
実際メーカーなどで使われている専門用語になります。
熟練のベテランでなくても入ったばかりの新人君でも鮮度が把握する手段はないのかなということで興味を持ちました。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
消費期限と賞味期限
食品にはなんらかの期限をつけなければいけません。
その期限には2種類あります。
消費期限と賞味期限
です。
消費期限と賞味期限はよく混同されがちです。
スーパー店員でもわかってない人多かったりします。
一般的に、消費期限は、品質が急速に劣化する食品に表示するものであり、賞味期限は、比較的傷みにくい食品に表示するものです。
東京都保健医療局HP
どんな違いがあるのでしょうか?
| 項目 | 意味 | 対象 | 期間の長さ | 備考 |
| 消費期限 | 安全に食べられる期間 | 鮮魚、精肉 | 比較的短い | 過ぎたら不可 |
| 賞味期限 | おいしく食べれる期間 | チョコ、米菓、缶詰、飲料 | 比較的長い | 過ぎたら不可でない |
- 消費期限は生鮮品などの安全に食べられる期間で比較的短い期限となり鮮魚、精肉が対象となります。消費期限を過ぎたら基本食べられません。
- 賞味期限は加工食品のようにおいしく食べれる期間で比較的長い期限となり、過ぎたものはすぐに食べられなくなるわけではありません。
我々鮮魚を扱う場合は基本消費期限です。
ただ塩干品で期限の長いものもあるのでその時は賞味期限を使うことになります。
ただしスーパーの表示は厳密に切り分けてない場合が多い点要注意です。
プリンターの印字の都合上どちらか一つになっていたりします。
これは実務運用的にもやむを得ないでしょう。
鮮度と鮮度感
- 鮮度・・・魚自体の新しさを示す客観的な状態
- 鮮度感・・・人が感じる感覚
この違いはまず覚えてほしいです。
その個体の持っている鮮度は変えようないですが鮮度感は変えることができるということです。
コレを理解しているかどうかで売り上げを上げられるかどうかも決まるといってもいいほどです。
同じような言葉ですが説明を聞けば内容が違うことが理解できます。
詳しくは下の記事をご覧ください。
\ ここをクリック! /
縮み(ちぢみ)
縮み(ちぢみ)ってご存知ですか!
マグロやカツオなどの冷凍魚を解凍してしばらくすると自然に形状が変わったりするものがあります。
朝どれの魚を三枚おろしにして皮を剥いて置いておくとまんまるな形になったりすることがあります。
これを業界用語で「ちぢみ」と言います。
いきなり違う形になってビックリしたりします。
これは鮮度がいい証拠で本来はいいことなのです。
しかし、いろんな事情があるようです。
下の記事で詳しく解説しています。
\ ここをクリック! /
調理と料理
調理と料理は言葉としては似ていますがちがいます。
どう違うのでしょうか?
調理と料理は、次のように定義付けられると思います。
- 調理(cooking) → 魚の原体を加工して三枚おろしや切り身の状態にすること。料理する過程のこと。
- 料理(dish,food) → その加工された状態のものに手を加えて食べ物(食べられる状態)にすること。出来上がったもの。
今回調理と料理の違いをしっかり確認してみたいと思います。
「さかなのさ 」初め魚屋さんがするのは調理が中心になります。
魚を加工することです。
なので素材を料理に提供するまでの過程を言うのです。
ここを理解すればなにをしてなにをしなくていいかがはっきりわかります。
「さかなのさ 」初め魚屋さんがするのは調理が中心になります。
魚を加工することです。
なので素材を料理に提供するまでの過程を言うのです。
ここを理解すればなにをしてなにをしなくていいかがはっきりわかります。
二杯酢と三杯酢と土佐酢の違い
魚を売っていると避けて通れないのがこの「合わせ酢」の違いです。
別に知らなくてもいいですが知っておいた方が何かと便利です。
この3種類の「合わせ酢」の違いをわかりやすく解説したいと思います。
簡単にいうと、
二杯酢は酢と醤油だけで作ります。
三杯酢はそれにみりんまたは砂糖が入ります。
土佐酢はカツオだしと酢を合わせて作ります。
いずれも自分で作れます。
詳しくは下記の記事で。
煮干しと田作り
煮干しと田作りは魚種というより作り方が違います。
煮干しは一度湯通ししてあるのに対し、田作りは生を水洗いしてそのまま乾燥させます。
これも知らない人多いと思います。
ここでしっかり覚えていってください。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
NET
NET(ネット)という表記をご存知でしょうか?
一般の方は知らないと思いますが水産物を袋単位で仕入れをする魚屋さんでは知っておきたい表記になります。
簡単にいうと「中身の重量」のことです。
これだけだとよく意味がわかりませんね。
中身の重量なら内容量という表記があるわけですから。
しかし内容量だけだと袋に入っている水分も入るのかわかりませんね。
そこで水分を抜いた純粋な中身の重量のことを「NET」と表記するのです。
例えば冷凍流通するベビーホタテや水の中に入っているムキ牡蠣などが流通するとき一袋1kg入といったような単位で取引されます。
これらは解凍したり袋を開けたりすると水分がたくさん出ます。
量ってみると実際は800gしかないということがあります。
800gしかないのに1kg(1000g)で計算したら200g分損しますね。
これを専門用語で言うと「歩留まりが悪い」ということになります。
別に確かに冷凍のままとか袋のまま量れば確かに1kgあるのかもしれません。
しかし取引のたびにこれどれだけ水分出るのとか確認するのも大変です。
意識して誤魔化しているわけではないでしょうがその辺曖昧なところがあります。
売る方も買う方も実際に入っている量が知りたいわけですから。
それで最近NET⚪︎⚪︎gというような表記がされるようになりました。
ということでNETというのは水分を抜いた実際の中身の重さのことなのです。
これはぜひ知っておいていただきたい水産専門用語です。
ばけ
有名な魚に似たような別の魚のこと
メジマグロ ⇔ コシナガマグロ
ヒネモノ(陳物)
ヒネモノ、ヒネという言葉水産の現場でよく使われます。
どんな意味でしょうか
簡単にいうと、去年の在庫品のことを言います。
魚は獲れる時期が決まっているというものが多いです。
で、その魚を加工する場合は獲れる時期に一年分をまとめて加工し在庫します。
それで一年持たせるわけです。
すると翌年またその魚が獲れる時期になると在庫が残っていたりします。
これを業界では「ヒネモノ」、「ヒネ」と呼ぶのです。
普通は新物ができると前の在庫の値段は下がります。
しかしながらその年たまたま獲れなかったりすると前の在庫の希少価値が上がり価格も高騰することがあります。
なのでヒネモノだからといって安くなるわけではないのです。
仕入れる時は状況を判断して買付する必要があるということです。
さらに詳しくい知りたい方は下の記事をご覧ください。
身焼け・ノリ・白太
魚を捌いていて身が白くなっていたり、やけに柔らかかったりしたという経験はないでしょうか?
これはいわゆる「身焼け」という状態です。
ノリとか白太(シラタ)と呼ばれたりもします。
まずはこういう言葉があるというだけでも覚えておいてください。
これは水揚げの際魚が活発に動きすぎて高温になり身質に変化が生じる時にこのような身焼けという状態になります。
病気や寄生虫が原因になることもありますが大半は体温が上がることによる身の変質です。
どんな魚がなりやすいか、身焼けの魚をどう扱ったらいいかについては次の記事で詳しく書いています。
興味のある人はどうぞご覧ください。
\ ここをクリック! /
ユニットプライスと定額販売
魚をパックして売るとき2つのパターンがあるのご存知ですか?
- 魚適当に入れてグラム売りをするやり方 〜ユニットプライス
- 魚の重さを量って定額売りをするやり方 〜定額販売
この2つを上手に使いこなせればばしっかり売上は上がってくれます。
基本は値段が高い時にユニットプライスでやって、値段が安価の時に定額販売を使いかます。
これを理解しているかしていないかで売上がガラリと変わります。
ここをしっかり押さえたい方は次の記事をご覧ください。
最後に
いくつか挙げてみました。
まだまだありますので都度追加していきたいと思います。
職場ではなかなか教えてくれないところなのでここでしっかり覚えていってください。
<終わり>
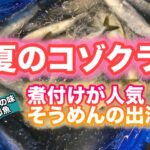








コメントを残す