生鮮品を扱う場合、中身の見えない商品は売れないというのが水産業界の常識です。
包装全体に色やデザインがついてたりして中身が見えない商品は売れないとされてきました。
例えば塩蔵海藻などは必ず中身の見える窓がついていたりします。
海鮮品の場合は品質の状態が購入動機の大きな部分を占めるので、見えないものは判断しようがなく避けられるからです。
実際私自身今まで相当数の水産加工品を仕入れて販売してきましたが、中身の見えない商品が売りにくいというのはリアルに感します。
包装パッケージをどんなにキレイにしても洒落た感じにしても中身が見えないものは避けられる傾向があるのです。
目次
グロッサリー商品は中身が見えることが最重要ではない
それに対して、グロッサリー、食品、日配の場合は中が見えない商品も数多く存在します。
そこでは素材よりも作っているメーカーがどこなのか、長年親しまれている商品なのかが重要になります。
缶詰や調味料などイメージするとわかりやすいと思います。
人工的に製造され品質が比較的安定していているものです。
商品としても生鮮加工品より素材感は求められません。
中身を見なくても中の状態が想定しやすいものです。
大事なのは信頼できるメーカーが作ったものか、長年愛用されている問題のない商品なのかが大きな判断材料になるわけです。
なぜ水産商品は中身が見えないと売れないのか?
素材感と言ったのは素材の個性のことです。
水産商品はそれぞれの個性が強いから中身を確認しないと売れないのです。
商品の特性上、個体ごとに差があり、同じものを想定できないからです。
大きさ、形、色合い、傷の入り方。
それぞれで違うのです。
それで水産商品は中身を見ながらでない買えないということになるのです。
水産売場で中身が見えないと売れない商品にはどんなものがあるか
今言ったように水産加工品は素材が非常に重要な要素になります。
例えば湯通し塩蔵わかめすなわち塩わかめが典型的な例です。
塩わかめは中身が見えないと売れません。
これはみなさんもご存じだと思います。
中身の見える青い袋に入って売られています。
それか中身が見える枠を作ってその中を透明にして中身が見えるようにしています。
本来塩わかめは蛍光灯の光に弱いとされているので中に光が入らないようにした方が商品管理は楽になるはずです。
しかし中身が見えないと売れないとメーカーもわかっているのであえて中身が見える小窓を作ったり透明の袋を使って中身を見せるようにしています。
素材を見せたいからです。
わかめも色合いから太さなどそれぞれ違うからです。
乾き物おつまみであってもそうですね。
鮮魚で扱うときは中身が見えるようになっていることが多いです。
コンビニの挑戦
ところが最近人気のコンビニの商品は中身を見せない商品化が図られています。
パッケージに商品のイメージ写真を載せてるだけです。
もちろん中身が見えません。
商品イメージなどの写真をつけたりはしていますが全く中身が見えないのです。
そして最近それらが順調に売れているということです。
これはどういうことなのでしょうか?
コンビニの中身が見えない商品の例
例えば、焼き魚は本来素材感が強い商品です。
鮭の塩焼きはどんな鮭なのかすごく大事です。
そうであるなら中身が見えるようにしないといけないはずです。
ところがコンビニでは中身が見えない包装パッケージにしているのです。
長年鮮魚小売りしてきたとしても中身が見えないというのは残念な結果に終わると思ってしまいます。
コンビニで中身が見えない商品が売れている理由
なぜ中身の見えない包装資材の商品が売れるのか。
それは、中身の素材が美味しいからです。
何度か食べていて味が食べる前にもうわかっているんですね。
要は中身が見えなくてもその商品が美味しければ売れるのです。
商品に対する信頼が出来上がっているということです。
特にセブンイレブンの商品力は抜群にいいように思います。
本当に旨いんですね。
それがわかっていれば例え中身が見えなくても売れていくということです。
そこでは中身が見える見えないというのは関係なくなるわけです。
まとめ
結局のところ消費者、利用者の信頼が得られているかがキーポイントになります。
その商品に対して信用を得られているなら売れるわけです。
消費者、利用者は多かれ少なかれそれだけ商品に裏切られたことがあるのです。
まさにそこを理解することが商品開発の本質要素になります。
自分達の都合で作られた商品は見向きもされません。
なので通常は中身を見せる工夫をしなければなりません。
よほど高度な信頼を得られてない限り、中身が見えない商品は売れないと考えるべきです。
小売りのみなさんがどう感じているかわかりませんが、今の時代でも素材が見えない包装パッケージの商品はできるだけ扱わない方が得策といえます。
素材が見えない不安は我々が思っている以上に大きいものだからです。
<終わり>



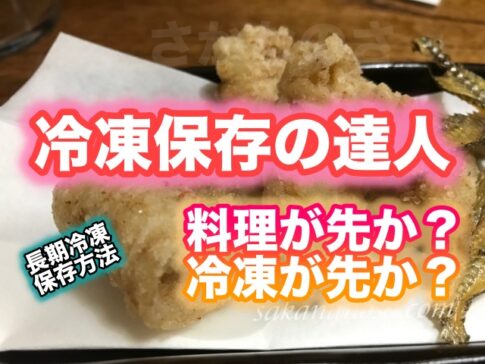





コメントを残す