年末も押し迫ってきました。
おせちの準備は順調でしょうか?
今回はおせち料理に入れる海鮮具材を一つずつ見ていきたいと思います
海鮮アイテムの入れ忘れがないかここで確認してみてください。
おせちには海の幸、海鮮料理が必須
タラやエビ、タイ、サケやブリがおせち料理に入っているのはよくみます。
それぞれ縁起の良さそうな魚です。
やはり海の幸が入らないとおせちも成り立ちません。
おせちにはマグロが入らない?!
ところでおせちにはマグロを料理したものが入っていません。
意外ですが確かに各社から出てるおせちパンフレットの内容をみても見当たらないようです。
これはマグロが必ずしも縁起いいとされてないことに関係します。
詳しくはこちらで

おせち料理はもともと神様に供える祝い料理
元々おせち料理は平安時代ごろ宮中で節の行事で振る舞われた祝い料理でした。
いずれにしてもおせち料理は神様に供える料理ということで非常に「縁起」や「いわれ」を大事にする料理ということです。
そしておせち料理に入る海の幸海鮮品は縁起のいいものでないといけないのです。
おせち料理に入る海の幸は基本縁起物
では縁起のいい海の幸にはどういったものがあるのでしょう?
通常おせちに入っている海の幸をみてみましょう。
数の子
数の子はニシンの卵の加工品です。
卵がたくさんついているので子孫繁栄につながって縁起がよいとされます。

いくら
鮭の卵の加工品のいくらもおせち料理に使われます。
上の数の子と同じく立派な卵なの
見た目の色合い良さもあります。
柚子の皮で作った器に入れられたものをよくみます。

煮エビ

煮エビは昔は車海老でしたが高騰したので今はブラックタイガー、さらにはもっと安いアルゼンチンアカエビなどが使われたりします。
いずれも腰が曲がるほど長生きしてほしい思いでおせち料理に入れられます。

祝い鯛

これは関西になりますが、おせち料理にはこの鯛の塩焼きが欠かせません。
ブリの照り焼き
ブリも地域によりますが出世魚なので照り焼きや煮付けにしておせち料理に入れられたりします。
地域によってブリでなくサケになります。
九州ではヒラマサを使うようです。
この辺は特に縁起がいいというより縁起悪くないといった感じでしょうか。
棒鱈煮

棒鱈煮は関西が中心ですが北前船の寄港地でも広く食べられているようです。
たらふく食べるという語呂合わせで一生食べ物に困らないようにという思いが込めておせち料理に入れられます。

酢だこ

酢だこは関東方面でよく食べられます。
タコはスミをはいて逃げるので苦難を取り除くという願いを込めておせち料理に使われます。
多幸という字を当てて語呂合わせにしたりもします。
酢にすることで日もちさせたいということもあるでしょう。
赤く着色したものと無着色と地域によって好みが出ます。
田作り

田作りはカタクチイワシの幼魚から作られます。
昔はこのイワシがたくさん取れたので田んぼの肥料にしたら豊作になったということで五穀豊穣を願ってこの田作りがおせち料理に入れられます。
小さい魚がたくさん使うので子孫繁栄を願うという意味もあるようです。
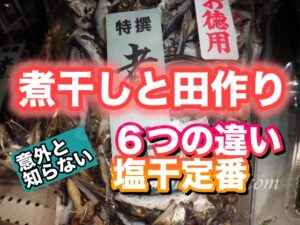
カニ
カニが爪を上下に動かす仕草が幸運を招き入れるようだということでラインナップに入ったりします。
確かにカニが入るととても豪華に見えますね。
カニの爪も入っていることがあります。
かまぼこ

かまぼこも魚肉のすり身からできています。
紅白にするとキレイですし縁起が良く見えます。
その他
野菜、和菓子などについての由来についてはここでは割愛させていただきます。
まとめ
おせちは縁起を担ぐ料理なのでやはりそれにふさわしい食材が選ばれます。
一つ一つちゃんとした由来があったります。
それらの全てが組み合わさっておせち料理ができ上がっているんですね。
一つ一つに思いを馳せながら食べるのも楽しいのかもしれません。
今年のおせちもおいしくできるといいですね。
<終わり>

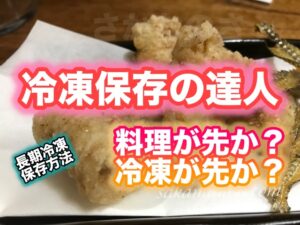


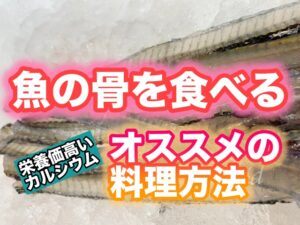



コメント